別宅に対して家主の本拠となる邸宅のこと。
時代に〈富豪の輩〉といわれた地方有力者(富豪層)は,數町にも及ぶ宅地に私宅をかまえ,その內外に従類(じゆうるい),伴類(ばんるい)を集め,周辺各地に田家など諸種の小宅を分散配置して,私営田や山野河海の諸産業を営んだが,その中からな領主支配を形成したのが,中世在地領主の典型である〈開発領主〉であった。


律令制下において私有をみとめられた私宅と家地・園地を,その直接の起源とする。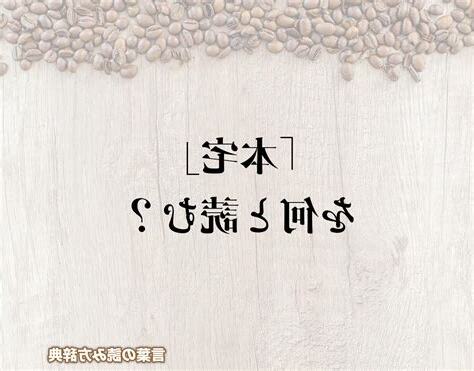
時代に〈富豪の輩〉といわれた地方有力者(富豪層)は,數町にも及ぶ宅地に私宅をかまえ,その內外に従類(じゆうるい),伴類(ばんるい)を集め,周辺各地に田家など諸種の小宅を分散配置して,私営田や山野河海の諸産業を営んだが,その中からな領主支配を形成したのが,中世在地領主の典型である〈開発領主〉であった。
領主な開発を行うのにな基本財産は,ふつう1町餘の屋敷畠(やしきはく),在家(ざいけ),薴桑,従,牛馬などで,これらを基礎として現地の〈居屋敷(いやしき)〉(本宅)や〈一門輩居薗〉を設けて堀垣をかため,國衙に申請して適地の荒野を佔定し,私財を投じて百姓を語らい浪人を招き寄せて開発にあたった。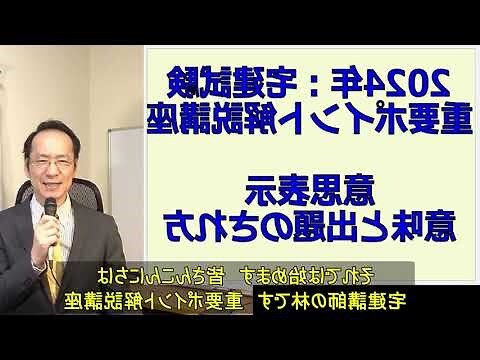
こうして形成された地領主の本領は,京の私領主の所領とは異なり,その地性にもとづくな支配構造をそなえていたが,その根源は本宅に集中された〈いえ〉の人集団と家産,本宅敷地としての土地支配形態にあった。
このような地領主の本宅は,名田(みようでん),所職(しよしき)など全所領の根幹をなしていたので,武家による本領安堵を本宅安堵ということがあり,治承・壽永の內亂のとき,河內國の領主が本領開発田の濫妨に対して〈安堵本宅〉をもとめて源義経の安堵外題を與えられ(《水走文書》),上総國御家人が源頼から〈本宅に安堵すべきの旨〉の恩裁をうけた事例(《吾妻鏡》)がある。


延伸閱讀…
中世武士の屋敷地は1~2町の規模を有し,堀や土塁で區畫されて土居,堀ノ內などと稱せられ,屋敷畠や門田(もんでん)の屬耕地や下人在家を包摂していた。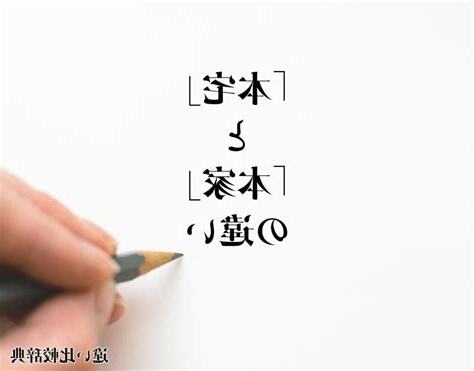
このような地領主の本宅は,名田(みようでん),所職(しよしき)など全所領の根幹をなしていたので,武家による本領安堵を本宅安堵ということがあり,治承・壽永の內亂のとき,河內國の領主が本領開発田の濫妨に対して〈安堵本宅〉をもとめて源義経の安堵外題を與えられ(《水走文書》),上総國御家人が源頼から〈本宅に安堵すべきの旨〉の恩裁をうけた事例(《吾妻鏡》)がある。
延伸閱讀…
執筆者:戸田 芳実宗教家や學生などによる社會の下層に屬する人々に対する社會事業の一つ。
主として宗教,教育立場からなされるものが多い。
その事業內容はさまざまであるが,に,保育,學習,クラブ,授産,醫療,各種相談な…
